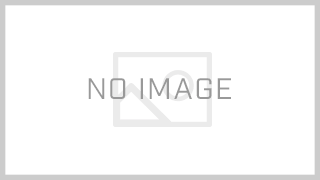医者の「とりあえず様子見ましょう」に感じた違和感と、その裏側にあるもの
先日、SNSでとある医療に関する投稿を目にしました。
症状がよくわからないからと、「とりあえず薬を出して様子を見る」と言う医者には注意。
セカンドオピニオンを取ることで、手遅れになるリスクを回避できる。「良い医者」とは、なんでも即答できる名医ではなく、
「わからないことを認めて、専門医に繋げられる人」である。
理学療法士なども同様で、知識不足を隠して自分の型に当てはめるのは、誠実さに欠ける。
一見“正論”に見える投稿に、もう一歩踏み込んで考えてみる
投稿の主張には非常に共感できましたが、同時に医療の現場にいる者として、
もう少し深く掘り下げて考えるべきポイントもあると感じました。
現実:一発で治せない理由がある
医療現場では、複雑な要因が絡む症状も多く、一度の受診ですべてを特定し、
完全に治療できるケースはそう多くありません。
- 原因が複数重なっている
- 体質・生活環境など個人差が大きい
- 経過観察が必要な病気や症状も多い
したがって、「様子見」という言葉には、
慎重な判断や、不確定な情報を整理するプロセスが含まれている場合もあるのです。
大切なのは「様子見」の背景にある意図
問題は、「様子を見ましょう」と言われた時に、
その意図や根拠が説明されないままになっている場合。
逆に、以下のような説明があれば、信頼の対象になることもあります。
- 「複数の可能性があるため、経過を追う必要がある」
- 「副作用のリスクを避けるため、段階的に薬を試したい」
- 「初期段階では検査に反映されない症例がある」
このような情報提供があるかどうかで、“誠実な様子見”か、
“逃げの様子見”かを見極めることができます。
「わからない」を認める勇気こそプロフェッショナル
本当に信頼できる医療者は、全てを即答する人ではありません。
良い医療者の特徴:
- わからないことを素直に認める
- 必要に応じて専門医や他職種に繋ぐ
- 患者にとってベストな選択を最優先する
これは医師だけでなく、理学療法士や看護師などすべての医療職に当てはまります。
自分の経験やセオリーだけで判断しがちな人は、視野が狭まりやすいので注意が必要です。
プライドと柔軟性の両立が「本物のプロ」
もちろん、専門職としてのプライドを持つのは悪いことではありません。
ただ、そのプライドが邪魔をして、誤った治療を続けてしまうケースもあるのです。
だからこそ、
「わからない」と言える強さと、
試行錯誤をいとわない姿勢が必要だと私は思います。
まとめ:医療の“正解”は、いつも一つではない
| ポイント | 意図・意味 |
|---|---|
| 様子見の背景を聞く | 医師の判断が慎重なものかを見極める |
| わからないを認める医者 | 信頼して連携をとる姿勢がある |
| 治療に正解は一つでない | 試行錯誤は医療の本質の一つ |
患者としても、医療者としても、完璧な答えを求めすぎないこと。
そして、誠実に向き合ってくれる相手を選ぶ目を持つこと。
それが、より良い医療を受けるために大切なことだと、あらためて感じました。